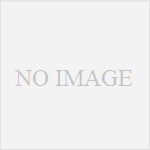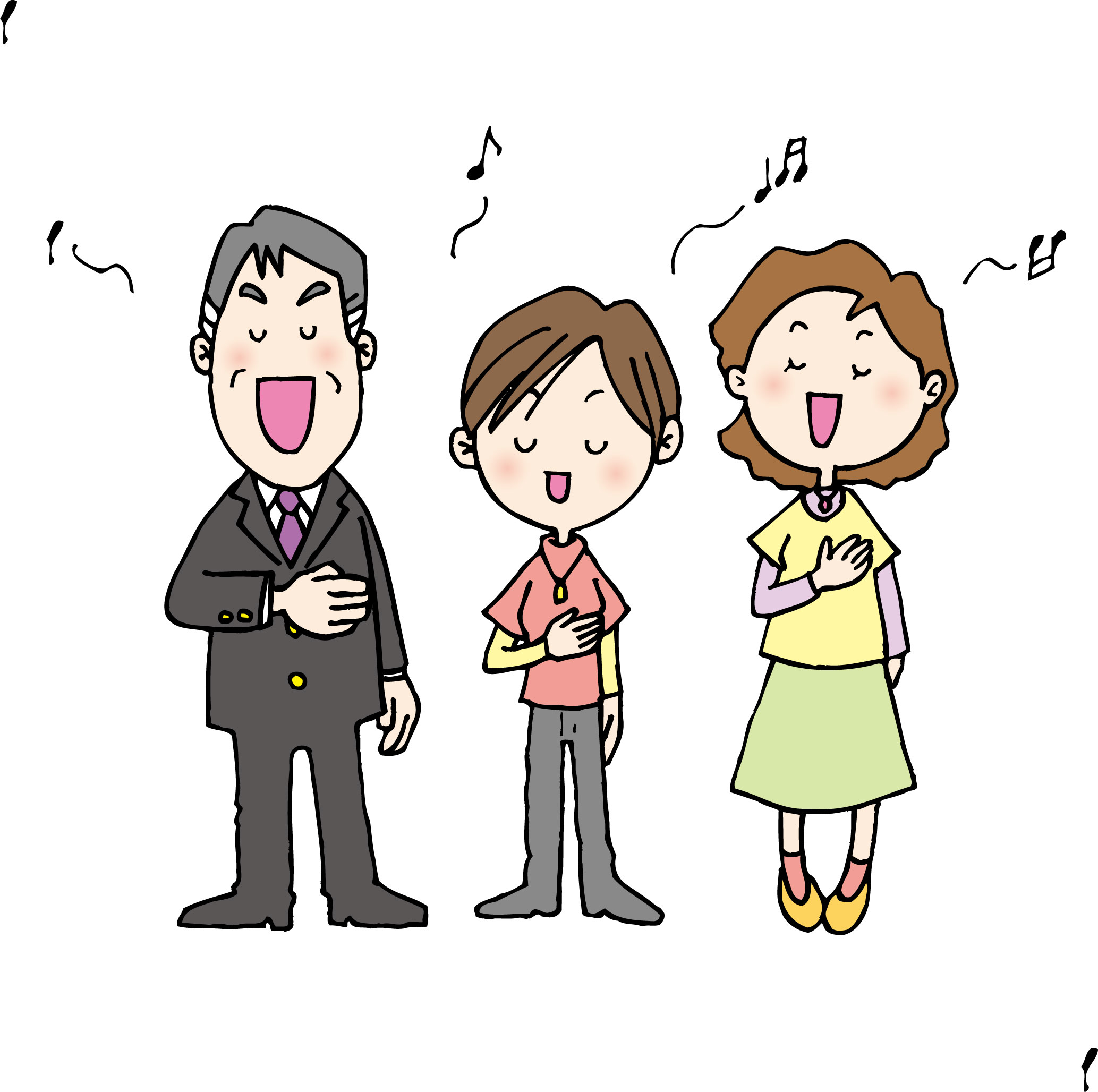何かしら音楽をやっていると、和音に興味を持つ場面もあると思います。
それで、
少し掘り下げると、どうやら和声学というものがあるらしい。
なんとしてでもこれを学びたい!!!
という風になることがあると思うのです。(そうじゃなかったらすみません笑)
でも、よくよく調べると、和声学を習得するには四声体の和声課題を解く訓練が良いらしいことにも気がつくと思います。
本当は先生につきたいのだけど、お金がないとか、どう探せばいいか分からないとか、先生に習うのがそもそも気が引けるとか、何らかの理由で和声学を独学したい人もいると思います。
残念なことに、これらの独学は大変難しいです。理由を2つ述べます。
自分の答案の禁則チェックが困難
和声課題を解くうえで、やってはいけない進行があります。
これを禁則と言い、並達1度、並達五度、並達8度、連続5度、、、など様々です。
自分で解いた答案に禁則が無いか、自分でチェックするのは困難でしょう。
なぜならば禁則が多すぎるというのと、自分がしたミスは自分で気づけないことが多いからです。
もし全部気づけてたとしても、そのチェックが間違っていないかやっぱり心配で、夜も眠れなくなってしまうでしょう。
さらに状況を悪くしているのは、禁則が許容されるシチュエーションも時にはある、ということです。(バステノールの並達1度など)
こんなの一人で確認するのは不可能です。
やはり音楽性を見てくれる人が絶対に必要
和声課題は学習が進んでくると、答えが何通りにもなってきます。
特にソプラノ課題など、人の数だけ答えがあるかもしれないです。(勿論それらは禁則を犯していない)
その様々な解の中には、音楽性に富んだものもあれば、音楽性が貧弱なものもあります。
これらの判断は、確かにあなたの感性でも一定のものが作れるとは思いますが、やはりプロの方にみてもらう方が良いのは火を見るよりも明らかです。
それでも、教科書に何かしら書いてあるんじゃないの? とおっしゃる方もいるかもしれません。
確かに、和声の教科書を読んでいますと「ソプラノは動きが豊富なものが良い」など、いくらかコツは書いてあります。
でも、音楽というものはそんなに杓子定規なものではありません。実際ソプラノの動きが少なくても豊富な表情を持った解もありうるのです。
和声課題には先生の存在が、ハイレベルを目指すのであれば絶対に必要ということになります。
まとめ
和声学を独学しようという方は残念に思ったかも知れません。
こうして突き放しておくのは私自身辛いので、一応、和声課題を独学することに向いた本を紹介しておきます。
『ネットで採点 和声学課題集Ⅰ』という音楽之友社が出している参考書があります。
この本に乗っている和声課題は、洗足のホームページで採点してもらえるという、びっくり仰天するほど便利なシステムです。
ただし、音楽性は採点対象外であり、あくまでも禁則が無いかをチェックする機能しかありません。
しかし、禁則を犯さない、ということ自体がそもそも困難ですから、これをコンピュータが採点してくれるのは有り難いどころの騒ぎではありません。
どうしても独学で勉強するんだ! という方は、この本を買うしか今は方法がないように思います。
以上です。