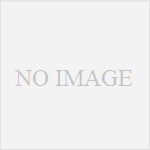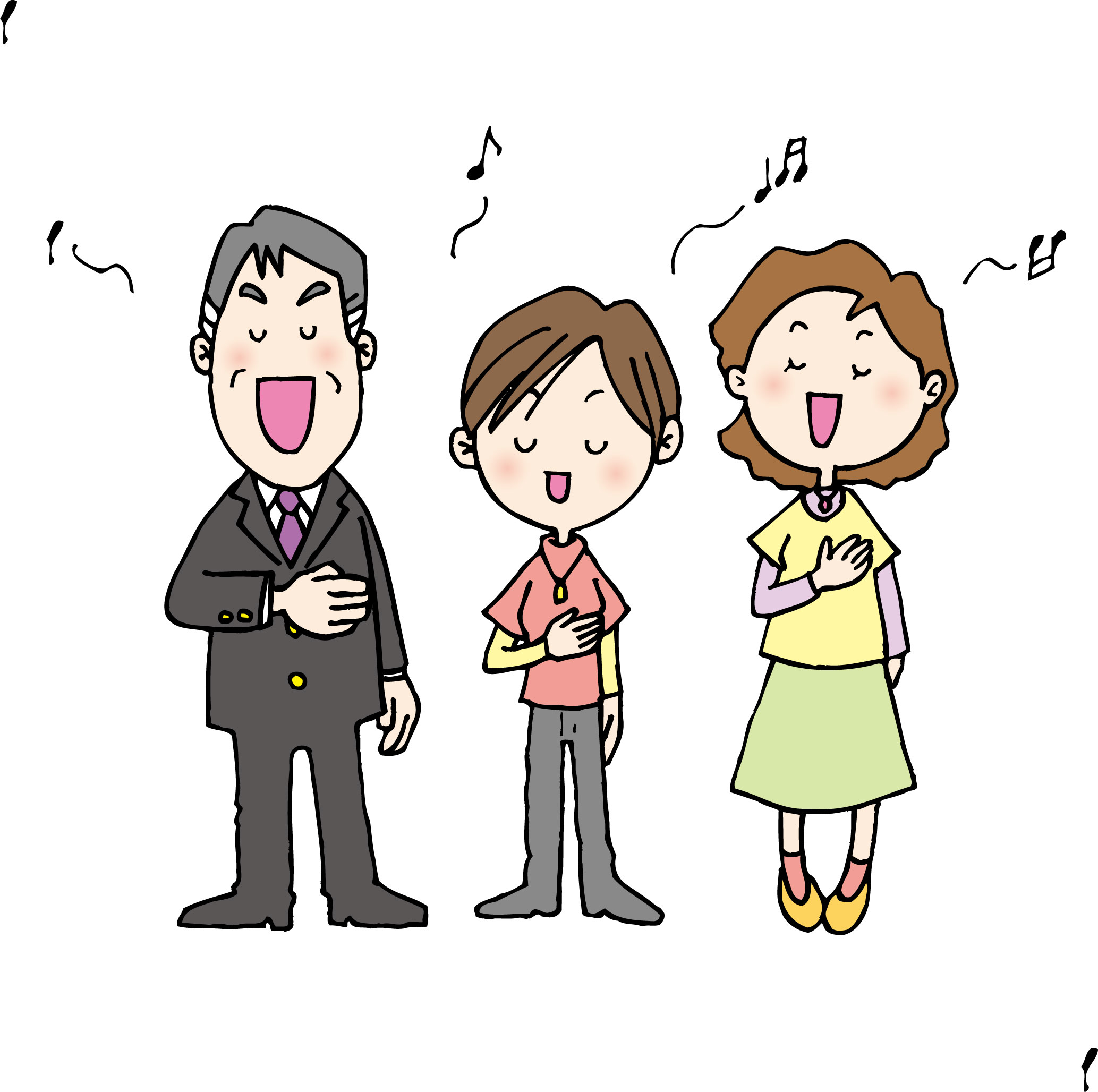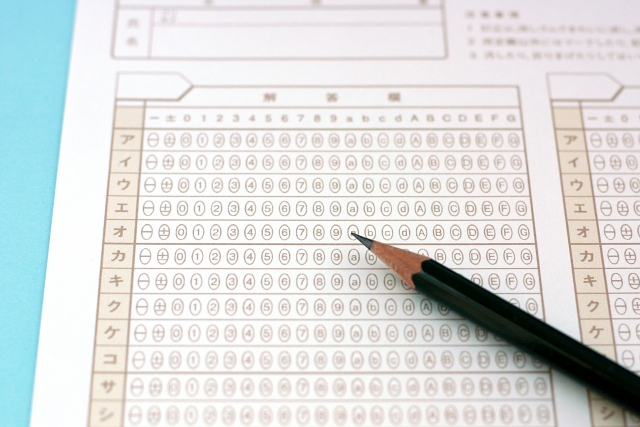前回の続きでございます。
2.楽器の持ち方の雰囲気を教える
弓の持ち方と同時に楽器の持ち方を教える必要があります。
まず、楽器の持つというのは初心者にとって結構きついことです。
私たち経験者の左腕は楽器を持つために最適化されており、特別な筋肉が発達しています。
この筋肉の中には日常生活に全く必要ないものもあります。
ですから、初心者はこの筋肉が発達していません。
このことがあなたにも簡単にわかる方法があります。
試しに右手で楽器を持つポーズをしてみましょう。
すると、楽器を持っていないにも関わらず、各所に痛みを感じるのではないかと思います。
(全く痛くない方は、左手とフォームが違っているか、筋肉がすごいかのどちらかです)
初心者は、さらに楽器を持ちますので、1分も待たないうちに限界を迎えることになるでしょう。(筋肉マンは除く)
また、左手で弦を押さえるために肘を体の中心方向に入れ込むと思いますが、これをやると腕がひねれてさらに痛くなります。
これを解決するには筋肉を鍛えるしか方法はありません。
しかし、最初から初心者にこの苦しみを味あわせるのは酷なことだと思います。
そこで、僕はこのように指導します。
まず、持ち方について簡単に説明します。
このとき、
- 楽器は正面に対して約斜め45°
- 弦が床と水平になるくらいまで楽器を上げる
- ヴィオラは大きくて重いため、ヴァイオリンと違って完全に肩に挟まなくてもよく、ある程度持ち上げてもよい
の三点を必ず伝えます。
本来ならば、弦を抑えるにあたって「手のひらと楽器の間隔は卵一個分」とか「肘をもっと入れ込む」とか気をつけなけらばならないことは残っているのですが、この段階でこれを教えると混乱を招く可能性があるので、僕の場合後回しにします。
つまり、楽器の持ち方の「雰囲気」を教えるのです。
そのあと、実際に弓で弦を弾いてもらうのですが、数分程度やって疲れてきたら、左手はもう楽な持ち方で良いことにしてしまいます。
3.開放弦のボーイングの原則を教える
まずは印象付けに。
開放弦は基礎ではありますが、初歩ではありません!!
本当に開放弦の指導を舐めてはいけません。
開放弦の指導は、すなわちボーイングの指導であります。
「ボーイングを制する者が弦楽器を制する」という格言があるように、ボーイングの技術はヴィオラを弾きこなすために必要不可欠なことです。
いくら左手が速く回っても、右手のコントロールが効かなければ、その左手のテクニックは無意味になります。
ボーイングあってこその左手の技術なのです。
ボーイングは重点的に教えなければなりません。
特に開放弦を教えるこの段階が一番大事になります。
開放弦でできないボーイングはそれ以外の状況でもできません。
開放弦を弾くときはボーイング以外のことを考えなくてもよいからです。
ここで、具体的に何を教えるかを僕なりにまとめてみました。
まずはボーイングの三大原則で、特に一番上が重要になります。
- 弓と弦は常に垂直
- 弓は指板と駒の真ん中くらい(例外があることも伝えておく)
- 圧力は腕の重みをかける程度かそれ以下(ヴァイオリンほどかけない)
これらを開放弦で完璧にできるようになることが非常に大事です。
とりあえずこの三点を伝えて実際に弾かせてみましょう。
なかなか教えた通りにはいかないと思います。
うまくできるようになるには、さらに細かいことを教えなければなりません。
例えば肘の高さ、手首の使い方、弓の速さなどです。
これらのことは次回の投稿に回したいと思います。
今日はこの辺でおしまい。
※「ボーイングを制する者が弦楽器を制する」というのは僕が勝手に唱えた言葉です。我ながらいいことを言った気がします。