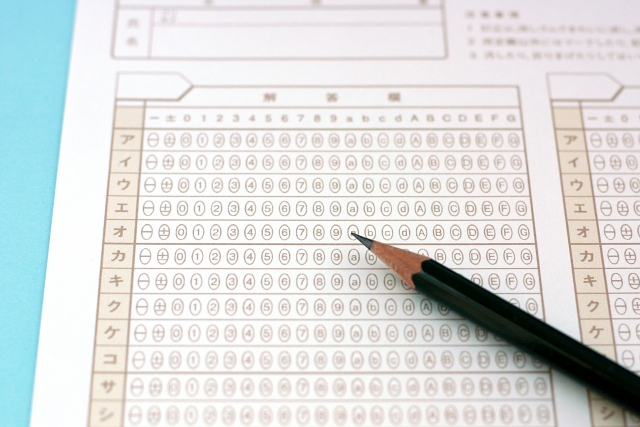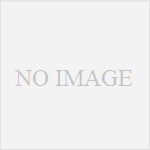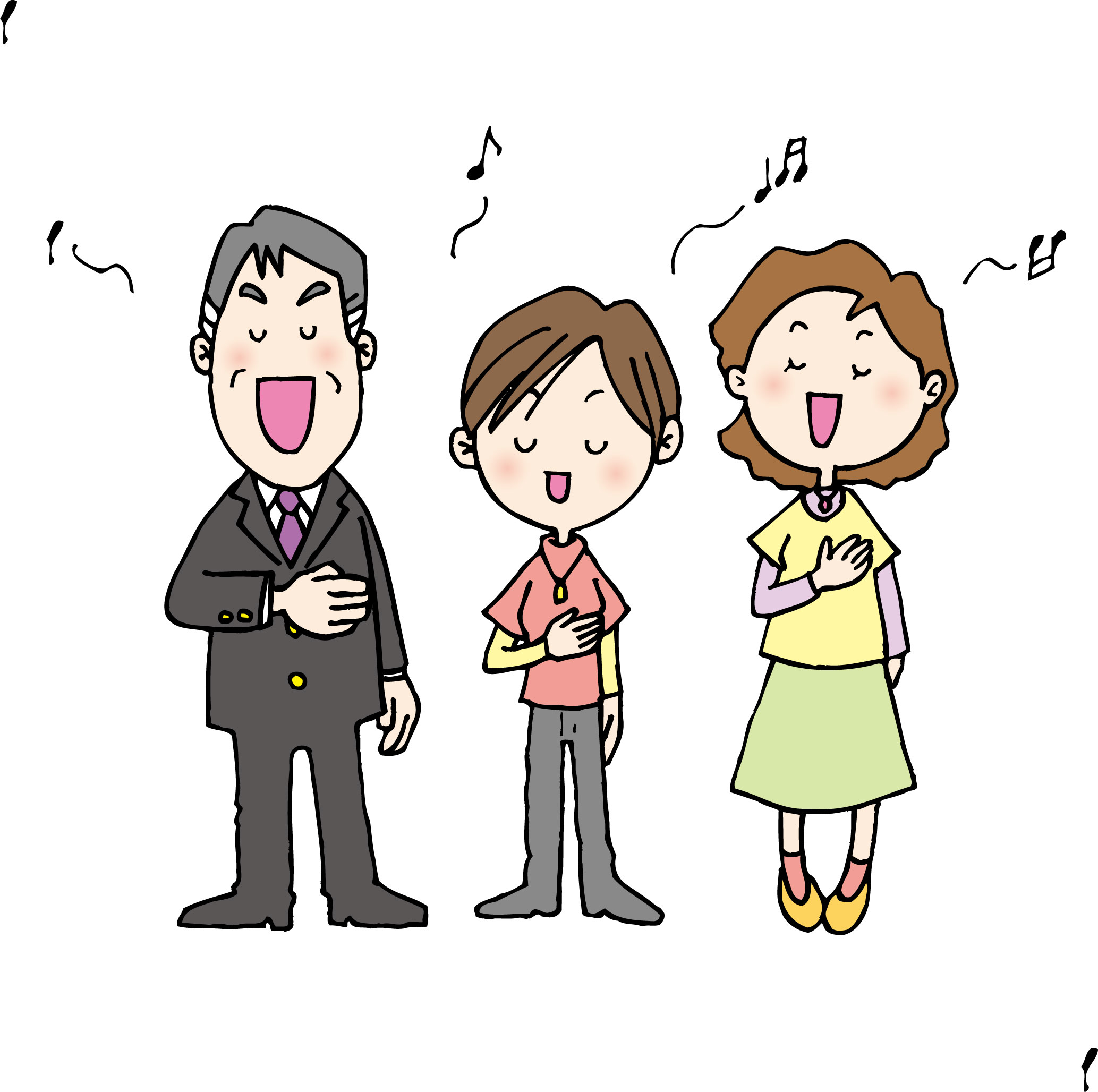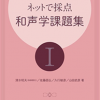いやにタイトルが偉そうになってしまいました。
わたくしのような本来ならばおとなしく教わっていればよいシロウトがこんなことを発信してはならないのではないか、という心の中の抵抗力も随分あったわけですが、ヴィオラを発信する身として最低限初心者指導について触れなければならないのではないか、という一種の勝手な使命感が勝り、ついに書き始めるに至りました。
世のアマチュアオーケストラにおいて、ヴィオラパートというのは弦楽器の中では特に初心者指導のノウハウが必要となってきます。
ヴァイオリンやチェロは小さいころから習っているお坊ちゃんお嬢さんが多いために、入部時には既に経験者である確率が高いのに対して、入部して運悪く?ヴィオラを持ってしまったような人は、そのほとんどが初心者なのです。
ヴィオラというのは譜面がヴァイオリンほど大変ではないし、チェロよりは機動性があるので、初心者にとって優しい楽器なのですが、それでも中途半端に難しい所もちょこちょこ存在するので、初心者のうちから基本を叩き込むことが非常に重要になります。
基本ができていないと、後々全く伸びなくなってしまうからです。
基本といったって、何年やってもできないんですけどね(笑)
とりあえず、初心者に初めてヴィオラを持たせた瞬間から、交響曲を何とか弾ききるくらいに育て上げる段取りを書いていきたいと思います。
1.弓の持ち方を教える
とりあえず、弓を持てないと音が出せないので、まずは弓の持ち方を教えましょう。
本来、弓の持ち方は人の体格によってまちまちなのではありますが、初心者に教える際は一番典型的な持ち方を教えることになります。
持ち方を教えるときは、自分の持ち方をベースに教えるのですが、その時に徹底しておきたい点があります。
- 小指を突っ張らない
- 親指をそらない
- 深めに持つ
1.の小指をそらない、というのは何があっても守らせなければならないポイントです。
小指はそえるだけ、というのを徹底しましょう。
小指が自由だと右手が自由になり、将来的に表現の幅が広がります。
2.の親指をそらない、というのも右手の自由度を阻害しないために徹底したいことです。
小さい音を出すときに弓を傾けるのですが、親指がそっているとそれがスムーズにできません。
3.の深めに持つ、というのは、ヴィオラ特有の指導になります。
ヴィオラを鳴らすにはそれなりの圧力が必要なので、それに負けないよう深く持つ必要があるということです。
深く持つのと浅く持つのとでは、後者の方が弓の自由度は高いですが、深く持った時の音の安定性と天秤にかけると、機動性よりも音の安定性を選んだ方が良いと考えています。
そもそもヴィオラの譜面はヴァイオリンほど機動性を求められていないので、そこは妥協してもよいと思います。
しかし、いくら理論を語っても、実際に初心者に教えてみると
その持ち方だと安定しないでござるwwwww手がプルプルしてきたでござるwwwwwwwwwいったん弓を机に置いたらもう再現できないでござるよwwwwwwwww
とか、
小指痛いンゴ!wwwwwwww小指は添えるだけとかどんな持ち方すりゃいんよwwwwwwwちょっとwwww教えてクレメスwwwwwwwwwwww
って感じになると思います。
こうなる原因は大抵、何らかのおかしい部分があります。
しかも、うまくいかない原因は我々の予想とは違うところに根差していたりします。
そして、力が入りすぎています。
そこで、そういったおかしな部分をよく観察することで見つけ出し、根気よく矯正していくのが大事です。
今回はこれくらい!
この先は次回に回します。次はもっと具体的に書くよー